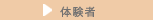「実は大腸がんを2回やっています。はじめが平成11年(1999年)6月、2回目が平成16年(2004年)7月。最初が直腸がんで、それが完治してちょうど5年目にまた大腸がんと診断されました。
はじめは症状として、便に血が混じるというのがしばらく続きました。そのうち、食事をするとすぐトイレに行きたくなってしまうというのがあり、それで病院を訪ねたのです。『がんかな・・・』と思いながら、『ひょっとしたら痔の簡単な手術で治るんじゃないか』と思って行きましたら、触診をした段階で、きわめて直腸に近いところに大きな腫れがあることがわかり、『すぐこの病院に行ってください』と言われて、その病院に行きました。
そこでいくつか検査をして、直腸から70mmぐらいのところに大きな腫瘍がありました。『組織を検査してだめであれば取り除く』と。取り除いたあとは、肛門がきわめて近い場所にあるので、『中でつなぐのは無理』で、『人工肛門を作ることになるでしょう』というお話でした。
組織検査のあと妻と一緒に行くと、『やはり悪性のがんでした』という先生からのお話があり、その時はびっくりするということではなかったです。もうそのまま『はい』と言って先生の言葉を受け止めたというか。先生が非常に優しい先生で、さらっと言ってくれたのですね。『人工肛門にしても、普通の人と同じように生活ができるから、心配することありませんよ』と、その言葉が暗示だったのでしょうか。『わかりました』ということで、覚悟を決めました。とは言いつつ、いろいろと悩んでしまいましたけど。
本当のところはどうなるのかなという心配はありました。でも、ぐずぐず考えていても仕様がないという部分もありましたので、まず先生にお任せして、先生の指示をきちんと受け止めて、手術なり治療なりをということでした。」
「(手術の当日)、『午後1時に手術室に入って、病室のベッドに戻れるのが午後6時ぐらい』と言われていました。すごく長い時間ですよね。どれだけたいへんな手術なのだろうと思ったのです。下準備をしてストレッチャーに乗ったときに、いろいろとお世話をしてくれる(スタッフの)女性に、『ベッドを温かくしておくから、いってらっしゃい』と言われたのです。『心配することないから頑張ってね』と言われると、逆に不安になったと思うのですが、その女性がにっこり笑ってそう言ってくれまして。『お願いしますね』と、ストレッチャーに乗りました。病院のスタッフの人というのは、患者を安心させて、不安を抱かないようにいろいろと訓練されて、それぞれみなさんが工夫して会話をしているのかなと、あとでじっくり考えてそういう気がしました。
全身麻酔ですから、麻酔が効き始めてあっという間にわけがわからなくなり、気がついたらベッドに戻っていました。声をかけられて、ちらっと目を開くと『あ、妻だな。子供だな』と思って、すぐまた眠ってしまいました。腰の辺りから脊髄の周りに麻酔薬を常時入れているので、痛くて痛くてたいへんだというのは、あまりなかったです。
翌日、先生方が代わる代わる来まして、『手術は予定通り、心配なく終わりましたよ。傷跡もよさそうだし、ストーマ(人工肛門)の状態も良好なのでよかったですね』と、3人の先生が次から次へと来て言ってくれるのです。『病院の先生というのは、魔法使いかな・・・』と思いました。そのちょっとした声かけがすごく安心したというか、ありがたいという感じがしました。」
「その後、ストーマの抜糸を約3週間後にしました。そのとき、主治医の先生からいろいろな経過と、今後の治療をどうするかという説明があり、妻と一緒に聞きました。
最初の直腸がんはステージ3bで、抗がん剤を長期間服用しますということで、確かUFT(一般名:テガフールウラシル)という薬と、サルノコシカケから作るという免疫賦活剤を処方されて3年間飲みました。副作用として下痢がときどきありました。我慢できない状態ではなかったです。特にお腹が痛くなるとか、膨満感というのはあまりなかったです。
その後は2ヵ月に1回、血液検査で腫瘍マーカーのチェックをして、基本的に1年に1回、腹部のCT、大腸カメラと胃カメラ(内視鏡検査)、MRI、脳のチェックを約3年間しました。」