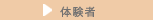「入院したのは家の近くの総合病院です。他の病院に行くという選択もあったでしょうけど、その頃はとにかく近いほうがよいだろうと思っていましたからね。あまり評判のよくない病院だったらしいけれど、本人はそんなのはあまり気にしていなかったから。
初期がんでしたから、体調は別にどこがどうというほどのことはなかったです。友達が見舞いにきても、『おーっ』てなもんで。『がんと言うので飛んできたけど、どうってことないか』というような状況でした。」
「手術のときはもう“まな板の鯉”です。とにかく『手術だよ』と言われて、『ああ、そうですか。お願いします』という感じでした。やっぱり女房が心配してね。本人はとにかくもう“お任せ”です。」
「“人工肛門を造る”ということを私は(医者から)直接聞いていないけど、女房がどこかで言っていたのです。あまりそういう記憶もないし、だいたい人工肛門なんてなんだかよくわかっていない状況ですから。女房が先生に、『若いから、できたら肛門の温存を』と言っていましたけど、先生は(私のを)見て『無理だ。もう人工肛門だ』という決め方をされていたようです。
その頃ですから、ドクターは患者が来たら自分の力量を試す、あるいは発揮するということにもなるでしょうし。そういう点では、タイミングよく飛び込んできた奴がいるという感じではなかったかなと思うのです。今は肛門温存とかいろいろ考えておられるでしょうけど、あの頃はがんというとほとんど(人工肛門造設)手術が多かった。今でも多いでしょうけど、そういう感じがしますね。
この人工肛門や人工膀胱というのは、手術としては非常に難しいというか、たいへんな手術になるのですよね。私も8時間半か9時間ぐらいかかっていますから。日本オストミー協会の顧問の先生方にお聞きすると、『皆(人工肛門や人工膀胱を)つけているからどうということないと思うかもしれないけど、やっぱり手術はたいへんだ』と言っています。単に(がんを)切り取ればよいだけではなくて、代わりの肛門を造らなければいけないですからね。」
「結局、手術では(人工膀胱造設のために、皮膚を)胃の上ぐらいからと、お尻 の後ろのほうまで切りますから、そっちのほうが(痕が大きくなり)たいへんだ なと思いました。(人工肛門は)脇に出口ができたという感じでした。こういうことは、なったらなった(で仕方ない)という感じも一面ありますので、私はそんなに動揺することはなかったです。
なので、(はじめは)装具についてほとんどわからなかったのですよね。だいたい、そんなものをつけると思っていなかったから。退院が間近になってから装具販売店の人が来て、『こういうものがありますよ』とサンプルを置いていって、それを使うという感じでした。」