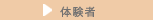「2〜3年前から『痔だろうな』と思ってずっとがまんしてきたのですが、平成11年の終わり頃からどうしてもがまんしきれなくて、肛門科に行きました。すると『あなたはうちに来る患者ではないよ。病院を3〜4ヵ所紹介するから、どこの病院がいい?』と言われて、ちょうど私の会社と自宅の中間にある病院があったのでそこにお願いして、紹介状を持って行きました。
その病院の先生がCTを見て『あ、これは・・。横になってください』と言ってすぐに自分の指で調べられて、『これは切らなきゃダメだ。肛門の近くに何かできているから。お尻がなくなるかもしれない』『え?なんですか?お尻がなくなるってどういうことですか?』『お尻がなくなることです』『え?』考えられないですよね。何の話をしているのかなと、当然、頭の中が真っ白になりました。『どうしたらいいの俺は?』
結局は先生から『悪性腫瘍です』と言われて、『悪性腫瘍というとがんのことだよな』と。今からちょうど11年前ですから、私の頭の中では『がん=死』というのがありました。」
「私は小さい会社をやっているものですから、『明日切りますよ』『はい、いいです』というわけにいかないのです。『先生、1ヵ月ぐらい手術するのを待ってくんないか。そうでないと、うちの会社がやばい。少し時間をください』とお願いしました。先生は『その代わり盛岡から一歩も離れてはダメだ。もし(腸が)破裂してしまったらばたいへんなことになるから、常にここにいなさい』と言われました。9月の頭にがんが見つかって、なんとか10月に手術をしました。
そのときには会社もある程度、仕事のいろいろな権限を譲渡した状態でした。『残った人間でやっていけ』と急遽1ヵ月で引き継いで、そのまま病院に行って『先生、ケリがついたからもう何とでもしてくれ』と。それと『極力お尻を残してちょうだい』とただお願いして、先生も『残せるだけ残す。でもダメなときは、ダメだよ。完治するためには全部とらなきゃダメだ。それを残してあとからまた再発があるよりもいい。それは私が手術をしながら判断するけども、それはいいかい?』って言われたので、『そりゃ任せます、でも残せるものならお願いしたい』ということで、手術台にのぼりました。」
「全身がおかしい感じ。それも3〜4日、5日間ぐらいだったと思います。あとは起きてみたら、変なところに穴があいているから、これがそう(人工肛門)なのかなと思って。看護師さんが入れ替わり立ち替わり見に来てこうしてああしてと教えてくれて、という生活を病院で2ヵ月ぐらいしていました。そのときに、腸の中の便を全部出す“洗腸”という作業を教わりました。
入院生活は個室を使わしてもらっていて、ちょうど冬場で日当たりのいい病室だったものですから、極力日に当たろうと思って、何もないときには裸になってベッドの上にごろんと寝ていました。
おしめみたいな、ふんどしみたいなものをして、ぷらんといるんですよ、ひとりで。それはそれで気持ちよかったですね。」
「神経が入り組んだところの手術だったそうで、いろんな神経に触ったり、メスの熱で神経がやられたりで、術後は少し排尿障害にかかりました。自分で尿を出すのに2〜3週間かかったと思います。ですからしばらく看護師さんにお願いして導尿していただいて、ことあるごとに看護師さんを呼んでいました。そのうち少しずつ尿が出始めてきて、カレンダーに毎日何cc出た、何cc出たと書いていくんです。だんだん量が増えていくと嬉しくなってきましたね。排尿障害は今でも多少残っていますけど、まだ私の場合、自分で出せるのでいいです。」