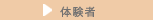「しびれもクールが終わったあと、だんだん取れてきました。でもすぐにではないです。しばらくは続いていました。全部取れるまでに何ヵ月間か掛かると言われていたので、実際にはどのくらい掛かったのかは覚えていませんけれど、2ヵ月間ぐらいはしびれていたと思います。だんだん春に近づいて気温が上がってきていたので、その点はずいぶん楽になったのではないかと思います。」
「化学療法はそれで終わったのですが、そのあともう一度手術をしました。でもそれは良性の腫瘍だったので、そのあとは何もしなかったです。
CT検査で、肝臓に黒い点があると言われて、がんの先生が仰天したわけです。『化学療法を行っている間にこんなものが出るはずはない』と言うので、日本の病院に一応問い合わせたところ、日本側は『いや、肝臓は大丈夫だった』とおっしゃいました。その黒点が大動脈の近くにあってかなり大きいということもあり、『手術をしたほうがいい』と勧められて、手術をしたのです。私はもうだめだと思いました。70%肝臓がなくなると聞いて、もうだめなんだろうなと。ただ、手術をしなかったらもっとたいへんなことになると言うので、やはり娘のことを思って『じゃあ手術します』と、4月のはじめに手術をしました。
私の看病に、米国にいる姉が1週間ずつ2回と、日本の姉が1週間来たのですが、結局手術をした時点で(肝臓を)取らなくても大丈夫ということで、切られて閉じられて病室に戻ってきました。目を開けたとき、娘に『ママ大丈夫だったのよ。がんじゃなかった』と言われました。1週間ちょっと入院していて、L字型にバサーっと切られてその傷口がすごく大きかったので、たいへんしんどい経験でした。がんじゃなかったからよかった、まだ生きられるという希望はもちろん湧いたのですが、肉体的にはもう本当にたいへんで、やはり傷跡が残ったのが非常にしんどかったです。」
「2007年の夏に日本に帰ってきたときに、手術をしていただいた病院で先生の診察をまた受けて、『大腸ファイバーは今回絶対にやろう』と言われてすると、2つポリープがありました。やはり『体質的にポリープができやすい』と言われました。カルチノーマ(上皮系悪性腫瘍)という説明を受けて、また公の病院で手術をしました。そのとき10日間ぐらい入院したのですが、そのあと化学療法は『しなくてよいです、もう大丈夫です』と言われました。それからはずっと検査できています。検査で万が一できていたらすぐに摘出ということで進んでいくしかないですよね。」
「なるべく普通に仕事をするということと、なるべく規則正しく生活するということを心がけているのと、歌の活動も結構やっています。それが自分の励みになったのと、音楽は非常に自分自身を助けてくれたということは感じました。
それと自分がものすごく強くなったというのはあります。今まであまり考えていなかったことも多かったのですが、なにかひとつ行動するときに『必ずやり遂げよう』と思うとか、『信念をもってやろう』とか、『その日をちゃんと充実して生きたい』とか。今までそんなことは全然考えなかったけれども、そういうことをよく考えるようになりました。なにか自分と同じように病気をしている人に対して、自分ができることがあったら貢献したいという気持ちが大きくなったというのはあります。」
「3食きちんと食べるということと、あまり繊維質のものを食べないこと。もちろん必ずお手洗いになるべく毎日、きちんと行くように心がけて。万が一、正常じゃないときは下剤を使うとか、でもなるべくきちんとその時間帯に行けるように、それはいつもものすごく心がけています。
普通に『お野菜ものをたくさん食べるのよ』とか『果物を摂りなさい』とか、『あまり肉を食べ過ぎないように』ということも、日本で言われたのですよね。自分ではそれほどお肉を食べたいとは思わないのですけど、ヨーロッパは肉食なので、皆さんお肉が好きで、家族もすごく好きなので、やっぱり週に3回ぐらいはどうしてもお肉を食べてしまう。だからあまり摂る量を多くしないように心がけるようになりました。
イタリア人は甘いものが大好きね。私はお料理が結構好きなので、ケーキなんかも焼きますが、自分は甘いものはあまり好きではないので、人のために焼くのです。娘の友達が来るとよくケーキを焼いてあげます。チョコレートケーキが大好きだから、チョコレートのたっぷり入ったのをよく焼きます。」
「この子をやっぱり守る、この子のために死ねないという気持ちはすごくありました。発病したとき、彼女は中学校1年生で小さかったから、もし万が一私が逝ってしまったらどうなるのだろうと思うと心配で、死ねないなという気持ちはすごくありました。彼女自身も優しい子だったので、私がはじめて日本で発病したとき、私の横で一緒に先生の話を全部聞いていて、彼女はハーフでそのときにどのくらい日本語が理解できたかわかりませんが、その先生が図に描いたりしたのを一所懸命聞くわけです。うちの姉や母がすごく心配した表情でいると、もう食いつくように私の病状を聞いてくるわけですよね。
私が手術する前の晩、病棟にいるときにはものすごく明るく優しくしてくれていたのですが、夜、実家に帰ると、『もし私に何かあったら・・』と泣き狂うような感じで、母や姉や弟(石油の仕事でサウジアラビアに行っていて私の病状を知って飛んで帰ってきた)も、慰めようがなかったと言うのですよね。でも翌日に病棟に来て、私が手術するときにはもうニコニコ笑っていたので、『すごく強い子なんだな』と思いました。
私の手術が成功したと聞いたときには、周りにいた看護婦さんもうちの娘の顔がパーっと明るくなったと言っていたので、それを聞いたときはすごく感激しました。だから絶対に生きてあげないといけない、自分の生きがいだと思っています。」