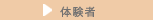「姉が平成17年(2005年)の夏に急死したんですね、脳内出血で突然。前の日まで元気に電話でしゃべっていて、次の日には意識不明になっちゃって。だからすごく『はかないな・・・』と思いましたね。人工透析をしていたので、自分の健康状態もすごく気を遣っていて、『あれだけ気を遣っていても一瞬でいなくなっちゃうんだ・・・』と思いました。かたや自分はがんを患って、何回か死の淵に出入りしながらも生きてこられたというのはなにか不思議な感じで、その分かれ目ってどこにあるんだろうと思いますね。
病院でも、入院してすぐに自分の死に場所を探していました。病院の中の渡り廊下をうろうろうろうろして。病院がお家から遠いので、『もし自分が緊急事態になっても誰も間に合わないかな』とか、『ここの病院できっと死んじゃうんだろうな』とか。死にたいわけじゃないのですが、最初に入院して放射線治療を受けている頃に、結構そういうことばかり考えていました。
かといって、死ぬとは思っていないんです。思っていないんだけど、『死に場所はここの病院なんだろうな』という矛盾した思いがありました。」
「でも主治医の先生が、私がどんなに悪い状態でもたとえば『もう危ないですよ』とか、そういうことを一切おっしゃらなかったんですね。危なくなかったのか、先生が治すという自信があったのかもしれないんですけど、私は自分の生きる命に対して疑うことはまったくなかったんです、なんか矛盾していますけど。とかく言いがちじゃないですか『状態が悪くて』とか、でも本当にそういうことを先生は言わなかったので、自分が死なないとは思わないけど、命に対しては疑いようがなかった。それがすごくありがたかったなと思いますね。」
「(入院中は)本当にすごくいろんな矛盾を抱えていたんですけど、昼間はすごく元気なんですよね。でも夜中にトイレに起きて行き、洗面台の大きな鏡に映った自分を見ると『ここにいる自分が現実なんだ』と我に返るというか、腕から点滴が出ていたり、やつれているので、『そうか私はやっぱり病院にいるんだ』と夜のたびに思ったりしていました。
昼間は鏡を見ても別に思わないですね。とにかく病院では元気に明るくしていました。けど夜になるとなにか隠された自分の本心が出るのか『そっかー。やっぱり夢じゃないんだ』という感じですね。だから本当に矛盾だらけですよね。」
「最初の5年間は本当にいろいろあったので、その頃は明日のこととか、たとえば子供たちがいくつになったときに自分がそばにいるとか、そういうことをまったく考えられなかったです。とにかくその日その日を生きるのに精一杯という感じで。もともとあまり計画性がないので、将来の計画を立てるということがないというのもあるんですけど。5年、6年経ってふと思ったんですよね、子供たちの未来に寄り添っている自分が見えるようになったって。『高校を卒業するのはあと何年で、そのときには自分もいくつになって』と、自分の未来もそこに一緒に見られるようになりました。」