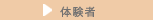「自宅でテレビをつけたら、『本当は怖い家庭の医学』という番組をやっていて、それまでは全く興味がないような番組だったのが、病気を機に『何をやるのだろう』と思って食い入るように観ていました。今日の先生はスキルス胃がん、腹膜偽粘液腫など腹膜播種のエキスパートだという紹介をされていて、その先生が手術をした画像も出たのです。
私は岩手の病院で1回目の手術が終わったときに『腹膜播種というのは、これ以上手術ができないんだ』という説明を受けて、私は『もう治療法がない』と受け止めていたので、(番組を観たときに)『私にとって、もうこの先生しかいない』と思い、先生の病院名とお名前を全部チェックして、翌日にはすぐ電話をかけていました。
病院にかけると(問い合わせが)殺到したらしく、『受付できない』と言われたのです。そうすると、これも運なのか、先生の番号を教えてくださって、先生が立ち上げられたNPO法人に登録されている携帯番号に『個人的にかけてくれ』と言われました。
かけたら先生が直に出られて、『私はこういう者』で『先生にお会いしたい。何とか助けてもらいたい』というお話をしたら、当時36歳という私の年齢とか、子供が小さいこと、小腸がんという希少がんであること、先生の長い医師生活の中でも小腸がんは6名ほどしかいなかったということで、『すぐにでも来なさい』と言われ、その瞬間に私の人生の分岐点がその電話で起きたという感じでした。」
「(診察は)予約をして2週間後ぐらいに行っています。先生自体は大阪の病院の先生だったのですが、静岡の個人病院に分院があり、月の第2週目と4週目にその先生がいらっしゃっていました。『岩手からなら新幹線で来られるのではないか』ということで、静岡のほうに来るように指示がありました。その2週間の間に『CTやMRの画像が持って来られるのであれば持って来てほしい』と言われて、用意して行きました。
もちろんセカンドオピニオンという形をとって(静岡の病院には)行きました。転院というより、岩手の病院の先生には『受けてもいいですか』とお願いをして、両方の先生に支えてもらうという形をとったので、私としては抵抗もなく、両方の先生に診てもらえるという、私にとっては非常にいい環境だったと思います。」
「『今の状況では手術をしないと予後が非常によくない』けれど、『すぐ手術をすれば助かるよ』と、説明的にはとても淡々としていて、それぐらいでした。手術をするための説明のほうがどちらかというと多くて、抗がん剤で最初はがんを小さくして、『僕の手術は目で見るものをすべてとっていく手術だから、なるべく抗がん剤で殺せていたほうが時間もかからず、手術の時間も短くて済む。あなた自身も楽なんだ』という説明を受けました。
入院先は先生が科をもっている大阪か滋賀の病院で、ベッドが空き次第そこに入り、『ある機械を使って42℃の抗がん剤で1時間お腹の中を洗う』という説明を静岡の病院で受けました。そして一連の説明のあと、『おそらく君は人工肛門にもなる』という説明を受けました。
平成19年(2007年)5月に体調を崩してから、ずっと否定的(ネガティブ)な言葉がすべてだった私に対して、『大丈夫だよ』という言葉を聞けたのがはじめてだったので、その瞬間は本当にうれしくて、終始泣いていました。帰ってくるタクシーの中も、東海道新幹線から東北新幹線に乗り継いでも、皆さんが私のことを見てもそれでも恥ずかしくもなく、パパの顔を見れば泣いていました。5時間に及ぶ新幹線の中でずっと泣きながら帰ってきて、お家に帰ってきて子供たちの顔を見て泣き、『ママ、大丈夫だって』と言って泣いて、おばあちゃんに説明して泣いて、もう嬉しくて泣いてばかりでした。」
「腹腔内に(ポートを通して)抗がん剤(ドセタキセル+シスプラチン)を入れるのは(静岡の病院に)通いでしました。実際点滴で入れるより、お腹の中に直接入れるほうが副作用が弱いと言われていたので、大丈夫だろうとは思っていたのですが、やはり髪は抜けてくるし非常にきつく、残りのクールは静岡の病院に入院して抗がん剤を入れていました。
岩手に戻ってきてもう一度静岡に行かなければいけないというときに、また腸閉塞になってしまい、(大阪の)先生が『腹腔内の抗がん剤治療は中断して、そのままもう手術をする』と言われて、はじめてそこで転院という形で、平成20年1月17日に岩手の病院を退院して、管をつけた状態で滋賀県の病院に転院しました。」