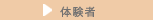「テレビで見た先生を目の前に、今後の方針をおっしゃっていただいて、手術が1月30日ということで、『10日少しあるから、その間にPET検査や血液検査など一連の検査を4〜5日で全部終わらせて、あとは手術までゆっくりと時間を過ごしてください』と言われました。『術後の状況次第で、あとは岩手に帰ろうねー』と先生に言われたような状況でした。
先生は口数は少ないのだけれども、すごく患者に対してウェルカムで『いやぁ、よく来たね。もう治るから安心して』とそれしか言わないので、本当に声を聞くだけですごく治っていくような気分になる感じでした。」
「ひとりだったので、すごく不安で、やはりちょっと怖いとは思っていました。手術自体が成功するかどうかとか、その腹腔内を42℃の抗がん剤で洗うというのも果たして成功するのかどうかとか、いろんなことをすごく考えていて。
そういった中、先生の患者さんも多くいらっしゃる病棟だったので看護婦さんが『先生の手術を受けた方はみんな元気になって帰っているから大丈夫よー』と言ってくれるのですよね。それは今思うと、果たして全員がそうだったかというのはわからないのですけど、そのときの私には勇気をもらった言葉でした。そうした看護師さんたちの言葉にも励まされたのもあり、術前はどこか苦しみながらも、痛みと絶えながらも、希望はありました。」
「まず術前のPETの結果はもう光り輝いており※、いたるところに腫瘍があり、それが全部ものすごく光っていました。先生の説明は最初の説明と若干ニュアンスが変わって、『PETの検査を見た結果、光っている部分があまりにも多く、直腸のところも非常に大きくなっている』。最初の岩手の画像から何ヵ月か経過していて腫瘍がまたさらに大きくなっているので、『大腸のかなりの部位をとる。できる限りすべてとる』けれども、先生の方針として、『僕はがん細胞を体内に残したくないんだ』ということで、『切れるところは切るから、術後はたいへんかもしれないけど、がんばって乗り越えよう』という説明を受けて、手術に臨みました。」
※PET検査で撮影された画像は、体のなかで病気のある部分が光って見える。
「医師には私は最後まで『人工肛門になるのはいやだ』というお話をしていたのです。でも『命を助かりたい、命をつなぎたいと思っている人が、そこで悩むのはおかしいだろう』というふうに言われました。『悩むところが違う』と。『人工肛門で悩むのではなくて、どうやって今後生きていくかということを考えなさい』と言われて、『そうだなぁ』と思いました。きっと私自身が30代というその若さとか、そういうところにまだしがみついていたのですよね。明日をも知れないと思っていたのに、そんな見かけを気にしたり何したりという自分に反省をして、『もうこうなったら仕様がないから、先生とにかく悪いところは全部とってください』とお願いをしました。」
「お陰様で、長時間の手術も無事に終わり、ICU(集中治療室)で目を開けたときは主人に『大成功だって。とり切れたそうだよ』と言われて、そのときはやはり涙が出ました。ただ人造人間のように首しか動かず、両方からの点滴もありぐるぐる巻きだったのですが、私はその瞬間自分の手のひらの手相を見たのですね。私は生命線がすごく短いので、そこが伸びているんじゃないかと思って見ると、なんとなく長くなっているような気がして。それを言われた瞬間、『すごい。私、生きられるかも』と自分の手相を見て思いました。」