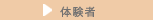「もともとそれほど激しい、がんだというような前兆があったわけではありませんでした。結婚した夫に『生理が重い』という話をしたら、『これから子供を産むわけだし、とりあえず一度病院に行ってみたら』と言われて、すごく軽い気持ちで近所の産婦人科に行きました。そこで先生に診ていただいて、はじめてがんだということがわかったのです。
診察をしたその場で先生に『これはたぶん、がんだね』と言われ、『自分はがんなんだ・・・』と思いました。まさかはじめて行った病院ではじめて会った先生に、『がん』と言われるつもりもなかったのですが、そう言われました。
そのとき自分はがんだという悲しさよりも、サラリーマンなので『仕事をどうしよう』というのがいちばん先に頭に浮かびました。県庁に勤めていて、それなりに自分の仕事もあったので、『この仕事を誰に任せよう・・』とか、『休まなきゃいけないのか・・』とか、そういうことばかり頭に浮かんでいました。だから先生に(がんだと)言われたときには、『先生、何日間休まなければいけないでしょうか?』と聞いたわけです。すると先生が、『何日間という問題じゃないね』と言われて、『とにかく今、がんだと言ったけれども、もう一度きちんと調べるから、もう1週間あとに来てください』と言われました。それで、その場は帰りました。」
「つまりそのがんの“怖さ”というのが、よくわからなかったのです。がんという言葉はあったけれど、先生が言うくらいだから、たいしたことはないのだろうと、結構たかをくくっていた部分もあるかもしれません。今もし同じ状況におかれて、これだけの知識があったら、とても冷静ではいられなかったです。
帰って、夫に話をしました。その日はたまたま職場の方たちが、夫と私の結婚のお祝いをしてくれる日で、夜そこへ行かなければいけなかったので、そのことを話している暇がありませんでした。『辛かったらよしてもいいよ』と夫に言われましたが、まさか皆がお祝いをしてくれるのに、いまさらキャンセルするわけにもいかないので、普通の顔をして行きました。」
「次の日、自分の母に話をしました。すると母は『結婚したばかりだし、相手に迷惑をかけるので離婚しなさい』と言いました。私もその通りだなと思い、相手を思いやれば思いやるほど、離婚しなければいけない、相手の人生を巻き込んではいけないと思いました。この子宮頸がんというのは、2人の問題ではなくなってしまうのです。子宮をとらなければいけないということは、子供が産めなくなるということで、それを考えると離婚しなければいけないと思い、夫に『離婚してほしい』と言いました。」
「確定的に『がんでしょう』ということでした。Ib期の腺がんで、広汎子宮全摘、しかも卵巣もリンパ節も郭清(切除)しなければいけないというお話を受けました。
先生にとりあえず『セカンドオピニオンがほしい』ということを話しますと、がん専門病院の先生をご紹介くださいました。そしてその先生のセカンドオピニオンを受けた結果、そちらの病院で手術をすることになりました。
診てくださった先生は、やはり(がんが)飛んでしまう、他のところに転移してしまう可能性が高いので、『なるべく早く手術したほうがいい』と言い、ベッドが空きしだい連絡が来るという話でした。そしてわりと早く、1週間もしないうちに連絡が来て、入院して次の週にはがんの手術をしていました。
元気なのですよね。普段と何も変わらないのです。今まで生きてきた自分と全然変わらないのに、ある日突然、検査をしたら先生に“がん”だと言われて、かなり大きな手術になる、手術しなければいけないと言われて、不安でいっぱいでした。それと、同じ病室に何人か同じ病気の方がいらっしゃって、お年を召した方が多かったのですが、弱っておられてたいへんそうだったので、自分はどうなってしまうのだろうと思うと、怖かったです。」
「何が何だかわからなかったです。昼なのか夜なのかもわからないし、自分が生きているのか生きていないのかすらよくわからない状態でした。それで3日ぐらい経ってはじめて、自分が何か大きな手術を受けたのだということを、だんだん実感してくる感じでした。
手術をした直後は術後病棟に行き、そのあと1週間ほどして普通の婦人科病棟に上がるのですが、その婦人科病棟に上がってから2週間ぐらいはお風呂に入れないのです。それでお風呂に入るまで、自分の傷を見るのが怖くて見ませんでした。夫は体を清拭(せいしき:身体をふいて清潔にすること)してくれるために見たのですが、私は現実が受け入れられなかったのか、しばらく見られなかったです。
(傷を見たときは)かなりショックでしたよね。怖かったです。血がついていて、何かくしゃみをするとそこが裂けてしまうのではないかと思い、怖くてしばらくくしゃみができませんでした。」